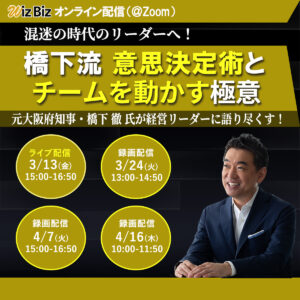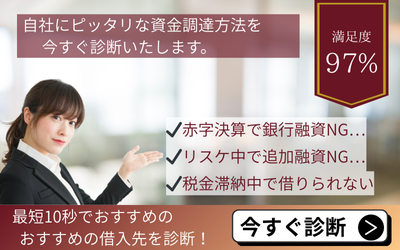本コーナーで掲載する経営者インタビューは、Podcast「社長に聞く!in WizBiz」で配信中の経営者インタビューを編集しています。今回、ご紹介する経営者は、鮄川宏樹氏(株式会社モンスターラボホールディングス代表取締役社長)です。(2023年8月23日 2023年8月30日 配信)
本コーナーで掲載する経営者インタビューは、Podcast「社長に聞く!in WizBiz」で配信中の経営者インタビューを編集しています。今回、ご紹介する経営者は、鮄川宏樹氏(株式会社モンスターラボホールディングス代表取締役社長)です。(2023年8月23日 2023年8月30日 配信)
今回は、株式会社モンスターラボホールディングスの鮄川宏樹氏にお越し頂きました。「多様性を活かし、テクノロジーで世界を変える」というミッションを掲げ、2023年3月に上場。世界20の国と地域でデジタルコンサルティング事業等を展開しながら、事業を通じた社会貢献にも意欲的に取り組むお姿から、経営のヒントが得られます。ぜひ、インタビューをお聞きください。
新谷哲:今回の経営者インタビューは、株式会社モンスターラボホールディングスの鮄川宏樹社長です。まずは経歴のご紹介です。コンサルティングファーム、テクノロジーベンチャーなどを経て、2006年にモンスターラボホールディングスを創業。同社は2023年3月、東証グロース市場に上場しました。鮄川宏樹社長、本日はよろしくお願いします。
鮄川宏樹:よろしくお願いします。
新谷哲:最初のご質問です。ご出身はどちらですか?
鮄川宏樹:生まれは広島なのですが、4歳のときに島根県の出雲市に家族で引っ越してきました。4歳から18歳まで、出雲市におりました。
新谷哲:小学校時代はどのようにお過ごしになられましたか?
鮄川宏樹:通信簿にはいつも「落ち着きがない」と書かれましたが、クラスの中で目立つタイプではなかったと思います。親の方針と、目が少し悪かったのもあって、ファミコンを買ってもらえませんでした。外で遊ぶとか、運動することが大好きな子どもでした。友だちともなるべくファミコンをしないように、外で缶蹴りするとか、野球するとか、そういう感じで遊んでいましたね。高学年になると、部活でサッカーをしました。
新谷哲:ガキ大将だったのでしょうか?
鮄川宏樹:いえ、大人しくはないですが、普通でした。そんなに目立つ方ではなかったと思います。
新谷哲:中学校時代はどのようにお過ごしになられましたか?
鮄川宏樹:野球部に入って、野球に明け暮れていました。野球の名門校や強い学校ではありませんが、当時の部活動には「しごき」がありました。グラウンドを何周もして水も飲ませなどの理不尽なこともありましたが、中学校時代は部活が中心だったかなと思います。
新谷哲:野球がお上手でしたか?
鮄川宏樹:好きでしたが、めちゃくちゃ突き抜けて上手い、みたいな感じではなかったですね。身体が小さかったので「2番セカンド」みたいな感じでした。
新谷哲:高校も出雲市ですか?
鮄川宏樹:出雲高校という、地元の県立高校に進学しました。
新谷哲:出雲高校時代はどのようにお過ごしになられましたか?
鮄川宏樹:普通科が10クラス、理数科が1クラスある進学校で、理数科にいました。普通科は男女比が半々くらいですが、理数科は40人中男子が35人みたいな男女比です。勉強中心ではありましたが、そのせいで悶々としたクラスでした。好きだった野球も部活でやり続けるのは厳しかったので、自分で軟式チームを作ったりしました。ただ、進路に迷っていた時期でもあります。飛び抜けて勉強に集中できていたわけでも、スポーツや他のことに打ち込んでもいない、人生で一番迷っていた時期だったと思います。
新谷哲:「将来、何になるのか」とか、そういったことに迷っていたのでしょうか?
鮄川宏樹:そうですね。思春期にありがちなことかもしれませんが「なんで生きているのか」とか「人生は何のためにあるのか」とか、そういう抽象的な悩みから具体的な進路の悩みまで、いろいろ迷っていました。両親は勤務医だったので継ぐ必要はないのですが、田舎で育ったので他の職業を知りませんでした。知らない職業は選択肢にはあがらないので「自分も医者になるべきか、でも、本当に医者になりたいのか?」と悩んでいました。
新谷哲:それまでに医師を目指されたことはありますか?
鮄川宏樹:反抗期の頃には、将来なりたいもので「医者以外」と書いたことがあります(笑)。そう言いながらも、他の選択肢がわかりませんでした。でも「医者にはなりたくないな」という気持ちが漠然とありました。父親は脳外科医だったのですが、リビングに1つしかないテレビで脳手術のビデオを見て「キツいな」と感じた経験もマイナスイメージに繋がりました。でも、医者は人の命を救う仕事だと理解していて、なりたい気持ちとなりたくない気持ちは半々くらいでした。その後、医学部を受験しますが現役での合格は叶わず、浪人してからは京都に出て寮に入ります。当時入った予備校の先生がすごく面白い方で、その方の影響を受けて教師を志すようになります。もともと数学が好きだったので、理学部の数学科に進学して、教職を取ることを選びました。
新谷哲:その後は神戸大学に進学されますが、大学時代はどのようにお過ごしになられましたか?
鮄川宏樹:大学時代はアイスホッケー部に入りました。北海道などの一部地域を除くと、大学で始める人が多いスポーツです。なので「新たなスタートが切れる」とアイスホッケーを選びました。また、アイスホッケーはフィジカルが物を言うスポーツで、展開もすごくスピーディーで面白かったので、見学した瞬間に「やってみたい」と思いましたね。
新谷哲:では、大学時代はアイスホッケーに打ち込んだのでしょうか?
鮄川宏樹:ええ。体育会系の部活だったので、かなりの時間をアイスホッケーに費やしました。大学のアイスホッケーって、スケートリンクをできるだけ安く借りる関係上、深夜に練習があります。夜11時からとか、遅いときは深夜1時からとか、そんな時間にアイスホッケーをやっていました。なので、大学時代はアイスホッケーとバイト、勉強はそこそこ、みたいな生活を送っていました。
新谷哲:私もアイスホッケーの試合をよく見るのですが、アイスホッケーは肉体接触が激しいし、ものすごい速度でパックが飛んでくるので、歯がなくなる人も多いと思います。そういったスポーツをやる上での恐怖感はなかったのでしょうか?
鮄川宏樹:おっしゃる通り、アイスホッケーは激しい競技ですが、私がやっているときは顎まで守られたフルフェイスのヘルメットをつける決まりや、防具がしっかりしていたので恐怖感は薄かったですね。もちろん、多少のケガはあるのですが、プロリーグで見るような派手な流血沙汰はありませんでした。
新谷哲:大学卒業後は、コンサルティングファームに就職されます。こちらに入ろうと思ったきっかけはありますか?

鮄川宏樹:もともとは教師になろうと考えていたのですが「島根といった一部地域から外に出たことがなくて、世の中の職業も、社会のことも、世界のことも全然知らない人間がいきなり教師になるのは、子どもたちにとって良くないのではないか」と思いました。それで就職活動を始めます。その後、コンサルティング会社という存在を知り「会社経営の根幹部分に携わることができるのか。これは自分に合っている」と感じました。また、コンサルティング業界はロジカルな世界なので、自分が得意な数字、いわば理系脳を活かせる分野だと思い、PwCコンサルティングに入りました。
新谷哲:PwCは世界でも一、二を争うほどの素晴らしいコンサルティングファームです。入社試験に数学があるほど、理系脳を求めている会社だと聞いたことがあります。そんな会社に入社されたということは素晴らしいことだと思いますが、PwCではどんな思い出がありますか?
鮄川宏樹:働く環境としてすごく先進的でした。最初からフリーアドレスで、自分の席がありません。ノートパソコンとPHSを持たされて「どこに座って仕事をしてもいい」という形でした。また、完全にペーパーレス化されていたり、アメリカでプログラミングやITの研修を3ヶ月やったり、非常に良い会社でしたね。仕事はプロジェクト単位で行うので、地方のプロジェクトにアサインされることがあったり「ルノーと日産が合併する」というシステム統合のプロジェクトがあって、フランスに行かせてもらったりもしました。すごくダイナミックな仕事をさせてもらえたと思っています。
新谷哲:PwCでは、どんなことを学びましたか?
鮄川宏樹:新卒入社なので学んだことばかりですが、一番大きいのは「仕事に対しての姿勢」です。ロジカルシンキングなど考え方のベースになる技術や思考力、プレゼンテーションスキルなど、そういったところを含めた基礎を作ってもらったように思います。
新谷哲:PwCの後はテクノロジーベンチャーに行かれますが、転職にはどういった理由があったのでしょうか?
鮄川宏樹:PwCは良い会社ではあったのですが「新しいイノベーションに関わっていきたい」という気持ちが強くありました。私の入社当時、1999年ごろというのは、日本で様々なインターネットサービスが出始めた黎明期でした。一方で、PwCのクライアントは超大手企業が多くて、オペレーション改善やダウンサイジング、リストラ、そのための大型システム導入といった仕事を行うことばかりでした。つまり「インターネット」というものには全く注目していない時代でした。もちろん、経営のオペレーション改善といったことも大事ですが「これは本当に社会に価値を生み出しているのか?」と考えたときに「新しいテクノロジーで世界を変えてみたい」と感じました。そのためには、自分自身が深くテクノロジーに精通しないとイノベーションに関われないと、思い切って転職を決意しました。
新谷哲:それで、イーシー・ワンに転職されたのですね。
鮄川宏樹:そうですね。イーシー・ワンは当時、100名規模の国内だけでやっているベンチャー企業でした。そこにエンジニアとして入り、シリコンバレーの会社が日本進出する際のジョイントベンチャーのコアメンバーとして参画したり、新しいテクノロジーを活用して、いろんな会社のeコマースや新システム、新プロダクトを作ったりしました。
新谷哲:コンサルタントからエンジニアに転職するというのは、なかなか大胆なことだと思います。周囲からの反対はなかったのでしょうか?
鮄川宏樹:反対はそんなにありませんでした。そもそも、周囲の人間も「何の会社かわからない」みたいな具合でした。PwCの先輩が止めてくれたことはありましたが、それ以外で反対はなかったですね。
新谷哲:転職に際しての恐怖感はありませんでしたか?
鮄川宏樹:それもありませんでした。ただ「育ててくれた会社に対して申し訳ない」という気持ちは多少ありました。しかし「自分が成長して貢献すべきは社会である。育ててくれた企業や先輩への感謝は忘れないが、最終的に自分が育って社会に貢献することで返す」と割り切って転職しました。
新谷哲:イーシー・ワンでの思い出はありますか?
鮄川宏樹:今だから言えることですが「月曜日に1週間分の着替えを持って出社して、会社に寝泊まりしながら仕事をする」みたいな生活をしていました。お風呂は近所の銭湯を利用して、眠るときはデスクの後ろに置いたキャンプ用の簡易ベッドを使って……本当に、起きている間は全て働いているぐらい、仕事に没頭していた時期でした。入社した数年後に上場するので、社内的にも忙しい時期でしたね。100人~200人ぐらいの規模感の会社で、経営層と距離がとても近くて、夜な夜な経営の方向性や事業についていろんな話をしたりもできました。
新谷哲:ハードワークですが、やりがいのある仕事だったのですね。
鮄川宏樹:ええ。仕事のやりがいに加えて、先見性のある会社で、いち早く中国に開発拠点を作っていました。2001年頃に中国拠点のプロジェクトマネージャーを任せてもらい、現地に行って人材雇用をし、日本と海外とで仕事ができる経験を積ませてもらえたのがよかったですね。当時は未開拓だった中国で仕事をして、そこから中国が発展していく可能性を肌で感じることができたのも、非常によい経験になりました。
新谷哲:イーシー・ワンの後に、モンスターラボを創業されたのでしょうか?
鮄川宏樹:いえ、イーシー・ワンに4年~5年いた後、もう一度コンサルタントに戻りました。コンサルタントという仕事自体が好きでしたし、テクノロジーの会社に行って技術を身につけて経験も積んだので「より上流の戦略コンサルティング会社に行ってみたい」と考えました。イーシー・ワンにいた当時、大前研一さんがやられている「ビジネス・ブレークスルー」と、オーストラリアのボンド大学とのジョイントプログラムである「ボンドMBA」を受講していて「将来的に起業という道もあるかもしれない」と考えながらMBAを取りました。その後、モニターグループという戦略ファームに入りました。そこに1年ほど在籍した後にモンスターラボを創業しています。
新谷哲:イーシー・ワンにいたときからMBAを取ったということは、すでに経営者を目指されていたのでしょうか?
鮄川宏樹:当時、私は28歳~29歳で「自分の将来は3つの道がある」と思っていました。1つは起業という道。1つはコンサルタントとして、より戦略的なところをやっていく道。もう1つは事業会社に入る道。どれも面白いなと思いましたが、そのときの自分にとって足りないスキルや足りないピースがありました。ITの深掘りはできましたが「ファイナンスやアカウンティング、マーケティングなどに関しては体系だって学んだ知識がない」という感覚がありました。それを補うためにMBA取得を考えました。しかし、そのためにアメリカの大学院などに行こうと思うと、受験するだけでも1年以上の時間がかかります。仕事をやめて海外に行くとなると、やっぱり3年~4年はかかります。すると「20代終わりから30代前半の3年~4年を費やすのはもったいない」という気持ちが湧いたので、通信で学ぶことを選びました。
新谷哲:MBA取得後、戦略ファームに入った後にモンスターラボを創業されますが、創業のきっかけはどういったものでしょうか?
鮄川宏樹:モンスターラボは、いわゆる「インディーズ」と呼ばれるアーティストの音楽を配信するプラットフォームを作るために創業しました。2006年に創業しているのですが、この事業アイデア自体は2002年ぐらいから考えていたことです。当時はインターネットが普及して、これまで書店に並ぶことがなかったマニアックな本がAmazonで売れるようになり、海外ではiTunesとiPodが登場して、従来のCDショップになかったような音楽が普及して「メディアレーベルに属していない個人でも自身で発信して、ニッチな音楽を聞き手に届けることができる」という時代でした。そういった多様な才能を持った人たちのための配信プラットフォームを作りたいと思い、そうした事業をやるために起業しました。
新谷哲:起業に対しての恐怖感はなかったのでしょうか?
鮄川宏樹:ありませんでした。別に、資産も家庭もないし、失うものはなかったんです。「スキルがあれば稼げる」と考えていました。ワクワクする気持ちしかなかったです。
新谷哲:創業時代にはどんなご苦労があったのでしょうか?
鮄川宏樹:楽しかったが苦労しかしていない感じです。最初に「モンスターFM」というインディーズアーティストの配信プラットフォームを立ち上げます。スタートは悪くなかったものの売上が上がらなくて、事業としてはうまく行きませんでした。2006年に創業して、2006年6月ぐらいにプラットフォームを出して、2007年には資金調達をしてVCも入ります。しかし、売上が上がらないのに加えて、資金調達も良い環境ではできず「あと半年で資金ショートして、このままだと潰れる」といった状況でした。「何かしら、お金を生む事業を作らないといけない」と、受託開発をやってお金を得て、そのお金を音楽配信のほうに投資して何とか生き延びていました。
新谷哲:上場は当初から狙われていたのでしょうか?
鮄川宏樹:狙っていたというより「お金を集めた以上は上場するしかない」という感じですかね。ベンチャーキャピタルからお金を投資してもらうということは、いつかはイグジットの機会を提供しないといけません。会社の売却は考えていなかったので上場しかありませんでした。
新谷哲:上場に際してのご苦労はありましたか?
鮄川宏樹:創業時の最初のプロダクトである音楽配信はうまくいきませんでした。それで受託開発を始めたのが2008年頃です。音楽配信を延命させる資金を稼ぐための受託開発でしたが、2013年頃に転機が訪れます。少子高齢化で日本の生産力が減少していく流れがある中、ITに関して言うとDXのように引き続き需要が大きく「非常に深刻なエンジニア不足になる」と言われていました。経産省も「2030年までにエンジニアが70万人不足する」といった発表をしていましたよね。その一方で、ベトナムやフィリピンやインドといった東南アジアを見ると、非常にエネルギーと可能性を持った若者が多く、彼らは仕事の機会に飢えているという状況がありました。日本だけでなくアジア全体で見ると、人口は増えているわけです。ならば「そうした海外人材を活用して日本企業のDXを実現する事業ができるのでは」と思いつきました。これは日本にとって本当に必要な事業になりますし、自分が音楽配信でやりたかった「個人の才能や多様性を活かす」ことを、世界のエンジニアやクリエイターをエンパワーする形で実現できると思いました。そこで、これまでやっていた音楽配信事業をデジタルコンサルティング事業へと転換して、当社の起点となる取り組みをスタートさせました。
新谷哲:2013年~2014年ごろに、今のモンスターラボに繋がる転機が訪れたのですね。
鮄川宏樹:ええ。そこから、かなりアグレッシブに資金調達をしたり、海外の会社を買収したりして、この10年間は年間40%ほどの成長率で会社が伸びています。苦労話をすると、海外の会社との統合ではすごく苦労をしました。「世界トップレベルのDXコンサルティング会社になるには、北米やヨーロッパという大きなマーケットに進出する必要がある」ということで、2017年にヨーロッパの会社を、2019年にアメリカの会社を買収します。組織的にもカルチャー的にも、マネジメントで非常に苦労しました。買収した会社の創業メンバーが抜けたこともありました。日本の本社との間に壁があって、ハレーションが起こることもありました。「どこまで統合していくか、どこまで自由度を持たせてアントレプレナーシップを大事にしていくか」のさじ加減でも悩みましたし、大変な苦労の連続だったと感じています。
新谷哲:ご苦労のかいあって、現在では30以上の子会社を抱えて、世界20カ国で展開している素晴らしい会社になりましたよね。
鮄川宏樹:そうですね。ファイナンスやコーポレートチームの貢献のおかげで、無事に上場することができました。非常にIPOの難易度が高い会社だったと思うのですが、みんなの力で上場できたのはよかったです。
新谷哲:海外の子会社を持っていると、上場の際にやることが多くなりますし、費用もそれだけ多くかかります。そのため、私のようなコンサルタントは「上場するなら、日本1社で」という言葉を良く使います(笑)。ですので、モンスターラボさんはコンサルタントの目線から見ても「逆境に負けず、すごい偉業を達成した」と感じています。そんな素晴らしいモンスターラボさんですが、現在はどのような事業をされているのでしょうか?
鮄川宏樹:DXを実現するためのデジタルコンサルティング事業をしています。システムインテグレーターがやっているようなシステム導入ではなく、顧客体験やUI/UX、そういった部分も含めたビジネスそのものの変革や、顧客体験の変革を伴うようなDXを得意としています。つまり「まだやることが決まっていない状況」から支援していく感じです。例えば「将来的に人口が減っていく中で、オンラインバンキングも含めて銀行業務が変化していくが、地銀はどういった形で変革していけばいいのか」などを経営目線、DX目線、ユーザー目線で考えて、新しい地銀のあり方やプロダクト、デジタルを活用したビジネスモデルの変革を支援している感じです。そして、プロダクトを出して終わりではなく、ローンチ後も改修・改善を繰り返したり、データ分析をしたり、戦略から開発、運用、グロースハック、データ分析といった部分まで一気通貫で引き受けております。それを日本だけではなく、ベトナムやフィリピン、バングラデシュといった世界中の人材を活用することで、ある程度までの低価格でも実現できるようにしました。それから、大手企業のお客様で言えば、海外にも事業展開されている会社が多数ありますが、そういう企業の海外進出やローカライズなどもサポートしています。

新谷哲:ここからは違う質問をいたします。事前に好きなこと、好きなものをお聞きして「物を持たないこと。古民家など、古い場所や古いもの。自然に触れること。自然の中に行くこと。社会を良くしようとする若者をサポートすること。ワークアウト」とお答えいただきました。自然やアウトドアがお好きですか?
鮄川宏樹:そうですね。山とか川とか海とかに囲まれた島根の田舎で育っているので、東京はもちろん利便性はあるし、いろんな面白い人に出会えるというメリットがある一方、ずっと都会にいると心が疲れるところもあります。なので、時間があるときは、自然があるところに行きたいと思いますね。
新谷哲:「若者をサポートすること」というお答えもあったのですが、この記事を読んでいる方の中にも、若くして起業を志す方がいらっしゃると思います。そういう方々を支援していきたい、ということでしょうか?
鮄川宏樹:私も48歳になりました。自分もまだまだ現役で頑張るつもりですが、やっぱり、未来は次世代を担っていく若い人たちが作っていくものだと思います。もともと教師になりたかったということもあり、機会をもらって母校で講演をさせてもらったり、地元の「TSKさんいん中央テレビ」が主催する企画を通じて、島根の若者をサポートしたり応援する取り組みを少しやっています。また、世界で言うとストリートチルドレンの支援にも携わっています。他には、社会起業をしたい人のサポートもやっています。別に上場するだけが全てではありません。世の中をより良くするために、身近な課題を解決するとか、地域課題に取り組むだとか、そういう活動をする方が最近増えてきました。そういった方や地元の方や、若い人からのご相談には、なるべく応えるようにしています。
新谷哲:座右の銘もお聞きして「座右の銘はありません」というお答えでした。しかし「生き方、経営で大切にしていること」ということで「誠実に生きる。人を大切にし、仲間を信じる。社会に、世界に貢献すること。会社の存在価値は、その会社がある世界とない世界の差分である。大きな目標から逆算して考える。一次情報を大切にし、現地で起きていることを自分で感じ、直接人と対話する」と回答いただきました。これは鮄川宏樹社長がずっと考え続けて、身に染みついていることでしょうか?
鮄川宏樹:そうですね。座右の銘だとパッと浮かばなかったので、普段から指針としていることや、考えていることをいくつか書かせていただきました。
新谷哲:弊社でも「誠実に生きる」ことの大切さを社員にはよく伝えていますが、この「誠実に生きる」というのは、どういった経験から思いついたのでしょうか?
鮄川宏樹:課題にチャレンジして、会社を経営していく中で色々な問題が起きます。会社が大きくなればなるほど、判断に悩むこともたくさん出てきます。そういう判断に悩んだときに「正しいことをやろうとしたか」が大事だと思っています。やっぱり「自分で社会を良くしていく」という信念を持って、少なくとも誠実に生きていけば、仮に会社の経営が上手くいかない時でも胸を張って生きていけます。その気持ちが、最終的には自分自身を支える芯になると考えています。
新谷哲:次が最後のご質問です。全国の経営者、これから起業する方に向け、経営者として成功する秘訣をお教えください。
鮄川宏樹:成功したというか、私どもは成長過程にあり、まだまだ課題だらけです。世界トップレベルのDXコンサルティングファームになる、という目標で言っても、まだまだスタートした直後だと思っています。とはいえ、20カ国に展開して、1つのマイルストーンとして上場も実現できたことで言うと「人から見ると無茶だと思うようなことでも、本気でやってみたらそんなに難しいことじゃない」と感じています。何か特殊な能力があったからできたとかではなくて、目標から逆算してアクションを取っていって、今があります。常識を疑い、自分で壁を作らずに、思い切って行動してきた積み重ねで現在があると思っています。あとは、カルチャーやバリューをかなり大事にしてきました。会社の理念やバリューに共感してくれる仲間が集まってくれていることが、会社の大きな力になっていると思いますね。
新谷哲:鮄川宏樹社長、本日はどうもありがとうございました。
鮄川宏樹:ありがとうございました。
編集後記
今回は、株式会社モンスターラボホールディングスの鮄川宏樹社長にお話を伺いました。戦略コンサルティングを学び、ITのエンジニアになられ、現在ではその両方を組み合わせたモンスターラボという会社を運営している経営者です。鮄川宏樹社長の素晴らしい生き方や考え方が、会社にも色濃く反映されているように感じました。20カ国に展開、上場もしているモンスターラボは、世界のDXを強くサポートしてくれる会社であり、裏を返せば、日本を引っ張っていける会社の1つであるとも言えます。鮄川宏樹社長の生き方、考え方を真似て、人生を良くしていきたいなと強く感じた次第です。これからも、世界を舞台にご活躍することを願っています。
鮄川宏樹氏
株式会社モンスターラボホールディングス代表取締役社長
コンサルティングファーム、テクノロジーベンチャーなどを経て、2006年に「多様性を活かし、テクノロジーで世界を変える」というミッションを掲げモンスターラボグループを創業。2023年3月に東証グロース市場へ上場を果たす。世界20の国と地域でデジタルコンサルティング事業等を展開しながら、パレスチナ・ガザ地区での雇用創出など、事業を通じた社会貢献にも意欲的に取り組む。また、2021年より地元である島根県出雲市のCDO補佐官を務める。
※本インタビューへの出演をご希望の方はこちらよりご応募ください。
本インタビューは、Podcast「社長に聞く!in WizBiz」で配信中の経営者インタビューを編集したものです。文中に登場する社名、肩書、数字情報などは、原則、収録当時のものですので、予めご了承ください。
今回は鮄川宏樹氏(株式会社モンスターラボホールディングス代表取締役社長)の経営者インタビューを取り上げました。
『社長の孤独力』抜粋版(PDF29ページ)
無料プレゼント中!
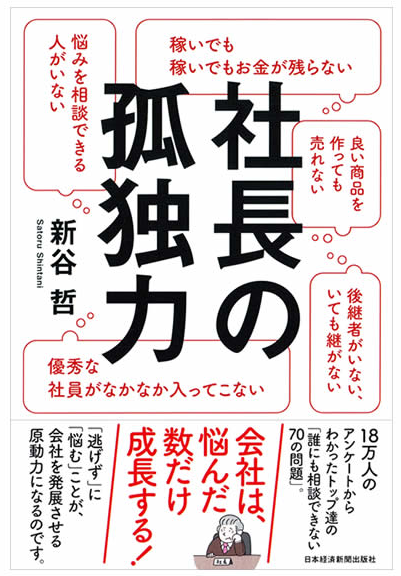 『社長の孤独力』(新谷哲/著) の【抜粋版】を無料プレゼントしております!
『社長の孤独力』(新谷哲/著) の【抜粋版】を無料プレゼントしております!
71の課題の中から「資金・人材・売上・採用・後継者」の5つを抜粋いたしました。銀行からお金が借りれない、社員がすぐに辞めてしまう、売上を伸ばしたい、など、具体的なお悩みの解決策が掴めます。ぜひご覧ください。
無料プレゼントの詳細はこちら