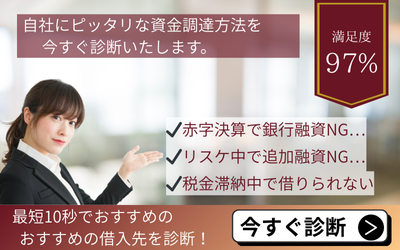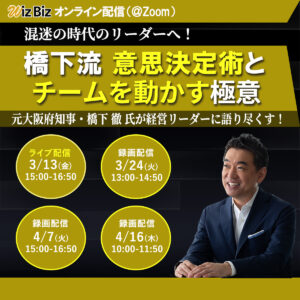本コーナーで掲載する経営者インタビューは、Podcast「社長に聞く!in WizBiz」で配信中の経営者インタビューを編集しています。今回、ご紹介する経営者は、松岡真功氏(株式会社BlueMeme 取締役会長)です。(2025年6月11日 2025年6月18日 配信)
本コーナーで掲載する経営者インタビューは、Podcast「社長に聞く!in WizBiz」で配信中の経営者インタビューを編集しています。今回、ご紹介する経営者は、松岡真功氏(株式会社BlueMeme 取締役会長)です。(2025年6月11日 2025年6月18日 配信)
今回は、株式会社BlueMemeの松岡真功氏にお越し頂きました。2009年にBlueMemeを創業。学生時代から25年近く取り組んできたローコード技術による業務システム開発の実現を推進。日本企業の課題解決を行いながら、上場へと導いたエピソードから経営のヒントが得られます。ぜひ、インタビューをお読みください。
※松岡真功氏はインタビュー当時、代表取締役社長の役職であっため、文中では当時の役職でお呼びしております。
新谷哲:今回は、株式会社BlueMemeの松岡真功社長です。まずは経歴をご紹介します。1998年、大学卒業後にソフトウェア開発会社でキャリアをスタート。その後、ネット証券会社、SAP、米サン・マイクロシステムズ日本法人を経て、株式会社BlueMemeを創業。2021年に同社を東証グロース市場に上場をさせております。松岡真功社長、本日はよろしくお願いいたします。
松岡真功:よろしくお願いします。
新谷哲:最初の質問です。ご出身はどちらですか?
松岡真功:熊本県菊池市です。
新谷哲:小学校時代はどのようにお過ごしになられましたか?
松岡真功:小学校高学年のころ、父が買ってくれたNECのパソコンに触れたのが、今の仕事に繋がる大きなきっかけでした。もともとはゲームがやりたくて始めたのですが、雑誌を見ながら自分でゲームを作ったり、パソコンごとに違うプログラミング言語を覚えたりしていました。
新谷哲:プログラミングは、中学でも続けていたのですか?
松岡真功:はい、中学でもずっとプログラミングをしていました。当時はまだインターネットはなくて、パソコン通信で大人とチャットしたり、自作ソフトを公開して意見をもらったりもしていました。周りに同じことをやっている人はほとんどいなかったので、ちょっと変わった中学生だったかもしれません(笑)。でも、この経験が「新しいものを作る面白さ」を知るきっかけになって、今の仕事にもつながっています。
新谷哲:すごい先進的な少年ですね!
松岡真功:当時は、パソコンを持っている人は「みんなやっている」と思っていました。私は温泉街の生まれで、周りにパソコンを持っている人はほとんどいませんでした。雑誌を読むとみんなやっているように見えたので「自分も同じようにやらなきゃ」と思い、いろいろなことを試しました。プログラミングのきっかけは、使い方がわからないので本屋に通ったことです。通学路にあった本屋に立ち寄った時に出会ったのが「ゲームセンターあらし」の「こんにちはマイコン」というマンガです。キャラクターがプログラミングについて説明する内容で、私が人生で読んだ数少ないマンガの1つです。それを参考にしながらプログラミングを学んだのが、中学時代の経験です。
新谷哲:高校時代はどのようにお過ごしになられましたか?
松岡真功:高校時代は、今の事業につながる経験が1つあります。文化祭で「マッチングサービス」をやりました。簡単に言うと、文化祭当日にコンピュータルームに行って学生番号を入力すると、自分と相性のいい異性の名前と学籍番号、そして「相性◯%」とハートマークが印刷された紙がプリンターから出てくる仕組みです。昔のプリンターなので1行ずつ「カッカッカッ」と印字されて、少しずつ名前が見えてくる。それがとても盛り上がって、行列ができるほど流行りました。これが起業を意識するようになった1つのきっかけですね。
新谷哲:今ではマッチングサービスはたくさんありますが、もしかすると松岡真功社長が先駆者だったのかもしれませんね。
松岡真功:その頃は起業しようなんて考えていませんでしたが、コンピュータを使って新しいサービスを生み出すことで、多くの人が動く。あの経験が「人に価値を提供するサービスを作りたい」という思いにつながっているのかもしれません。
新谷哲:大学はどちらに進学をされましたか?
松岡真功:大学は福岡です。実は私の家系は教育一家で、母方は多分江戸時代以前からずっと教師をしています。私が覚えているのは、祖父が校長先生だった頃ですね。姉も教師をしていました。いわゆる教師家系です。そうした背景もあり、教育学部に進み、物理学を専攻しました。本来ならこれだけパソコンをやっていると情報工学部に進むと思われるかもしれませんが、私は独学でやっていたので「わざわざ大学でやらなくてもいい」と思っていました。
新谷哲:大学時代は教師を目指されたのですか?
松岡真功:いえ、全く思っていませんでした。むしろコンピュータを使って仕事をしたいと思っていました。当時はコンピュータグラフィックスやコンピュータ音楽が流行っていて、作曲をしたり、CGを作ったり、そういう「アート系とITの融合」に強く惹かれていました。そのため「教師にはならない」と心の中で固く決めていました。
新谷哲:大学時代もやはりプログラミング中心の生活だったのでしょうか?
松岡真功:そうですね。ITの知識があったので、大学時代はアルバイトで活かしていました。新入社員研修の講師をしたり、WordやExcelの使い方を教えたりしていました。また、子ども向けには幼稚園〜小学校低学年向けのPhotoshop・Illustrator教室を、高齢者向けには70歳〜80歳の方々にMacでお絵かきをする教室を開いたりもしました。気づけば「教師」をしていましたね(笑)。
新谷哲:小学校高学年でプログラミングに触れて以来、ずっとITの世界にいらっしゃったのですね
松岡真功:そうです。小学生のころから触っていたことが大きなアドバンテージでした。コンピュータを扱うことに全く抵抗がなく、ストレスも感じませんでした。生活の一部として自然に存在していたので、それを活かしてアルバイトもできるし、お金も稼げる。大学時代はそんな形で過ごしていましたね。
新谷哲:大学卒業後、最初の就職はソフトウェア開発会社とのことですが、やはりプログラミングのエンジニアとして入社されたのですか?
松岡真功:はい。大学時代にアルバイトをしていたとき、セミナーのお手伝いをすることがありました。有識者が登壇して「これからのITは〜」という話をするセミナーですね。その際、オペレーターとしてインターネットの設定などを担当していました。そうした現場には私と同年代の人が多くいて、最後に会食がありました。高級な料亭に連れて行っていただき、フグのコースをいただいたのを覚えています。学生だった私は食べ方もよく分からず、横にいた店員さんが1枚1枚巻いて皿に置いてくれるような店でした。そういう場で交わされる会話を聞いて「面白いな」と思いました。その場にIT業界の経営者の方々がいらして、その中の1人の社長に誘われ、そのまま就職しました。実は就職活動はしていません。

新谷哲:ソフトウェア開発会社での思い出はございますか?
松岡真功:思い出深いのは、やはり社長ですね。私が初めて出会った社長であり、社会人として最初に接した経営者のモデルとなった方です。とてもユニークな人物でした。例えば、接待といえば普通は料亭などを想像すると思いますが、その社長は車で海岸沿いに行き、お客さんを連れて七輪と食材を持ち込み、海辺で鍋をやります。周囲はカップルが夕日を眺めながら語り合っているようなデートスポットで、私たちは地べたに座って鍋を囲む(笑)。しかも照明を忘れてしまい、日が落ちると七輪の火だけを頼りに食べたという記憶があります。こういう“変わった接待”をする社長で、「新しいことをやりたい」という方でした。その姿勢がとても印象に残っています。
新谷哲:その後はネット証券会社で独自システム開発をされていたと伺いましたが、どのような経緯で移られたのでしょうか?
松岡真功:転職ですね。最初はベンチャー企業に入り、社員5人ほどの小さな会社で開発をしていました。小さい頃からプログラミングをやっていたので「先輩を追い抜きたい」と必死に頑張りました。頑張れば頑張るほど能力が伸びて、もっと上を目指したくなる。エンジニアってそういうものですよね。その頃、「今後世の中を変えるようなシステム開発をしたい」と思うようになりました。ちょうどネット証券が台頭してきた時代で、「金融はITの塊だ。ここから大きく変わる分野だ」と感じます。ITとの相性が抜群に良い金融の世界に飛び込んでみようと思ったのが、ネット証券会社への転職のきっかけでした。
新谷哲:ネット証券会社での思い出はどんなものがありますか?
松岡真功:在籍期間は1年ほどでしたが、とても印象深い経験でした。かなりのハードワークで、朝早くから夜遅くまで働き、月曜から金曜まで取引があるので、ザラ場中は基本的に監視。休憩時間にプログラミングをするような生活でした。その中で、今の事業モデルにつながる大きな出来事がありました。当時はまだスマホがなく、携帯で株取引ができるアプリを作ろうというプロジェクトがありました。iモードの後に「iアプリ」というのが登場したのをご存知でしょうか。そのiアプリ対応端末が発売されるタイミングで、最初に作られるアプリはほとんどがゲームでした。実用的なものは少なかったので、「金融取引、株取引のアプリが作れたら絶対に需要がある」と思いました。ちょうどその頃、会社は外注に調査や開発を依頼していました。出来上がったものを見た時に、「いや、自分の方が絶対いいものを作れる」と思ってしまいました。若かったので、生意気にも(笑)。そこで本部長クラスの役員の方に「これ、いくらで頼みますか? 今後どれくらいかかるのですか?」と聞いてみました。すると結構な金額でした。そこで「私が作れるので、1ヶ月〜2ヶ月ください」とお願いして、実際に1人でアプリを作り切り、リリースまで持っていきました。その時に分かったのは、「開発は、作りたいものとシステムを理解している人が1人で作るのが一番早い」ということです。この経験が「少人数で素早く、自動化を駆使してシステムを作る」という今の事業モデルに繋がります。これがネット証券会社での一番大きな思い出ですね。
新谷哲:その後、SAPにお移りになったということですね。移られた理由は何かあったのでしょうか?
松岡真功:ネット証券はかなり大変でしたし、東京に出てくると本当にいろんな情報が入ってきて、さまざまな業種があることを知りました。その中で私が一番気になったのは「業務システム」という領域です。エンタープライズシステムと呼ばれるものですね。多くの会社が導入しているのに、普段の生活や学生時代にはまったく触れる機会がない。会社に入らないと分からない領域ですよね。販売管理、生産管理など、企業が必ず使うアプリケーションが揃っている。ここを知ることができれば、ビジネスのチャンスが広がるはずだと感じました。最初に入った会社の社長にも「起業しろ」と言われていましたので、「この領域なら将来起業できるのではないか」という思いがありました。そうした調査や興味から、SAPに移ったのがきっかけです。
新谷哲:SAPでの思い出を教えていただけますか?
松岡真功:SAPでは主にコンサルティングチームに所属していました。そこにはバリバリのプログラマーがほとんどおらず、私が少しでもプログラミングをすると、すごく驚かれます。「そこまでやらなくていいから」と何度も言われ「え、やらなくていいの?」と不思議に思ったくらいです。よくあったのは、SAPはドイツの会社なので、ドイツ語から日本語に翻訳したアプリケーションを動かすのですが、日本語版だとうまく動かないことが多いです。その原因を調べて「ここをこうすれば動きます」と報告すると「そこまでやってもらうと逆に困るから、もっと軽い調査でいい」と言われました(笑)。それでも自分は徹底的にやっていましたね。ただ、それは一部分の話で、SAPのプロジェクト自体はとても大規模で、多くのコンサルタントと一緒に企業が抱える課題に挑むものでした。非常に印象深い経験です。
新谷哲:その後ベンチャー企業に移られて技術開発をご経験されたとのことですが、どのような会社だったのですか?
松岡真功:これは、スマートフォンが普及する少し前、新しいモバイルが流行し始めた時期のことです。今でいうM2M、つまりマシンtoマシンで機械同士が通信し合い、新しいサービスを提供しようという会社でした。例えば、お店に入るとそのお店のクーポンが携帯に届くといった仕組みです。今ではGPSを使ったサービスが当たり前ですが、当時はそうしたものがまだなかった。そうしたプラットフォームを作ろうという会社に、エンジニアとして、またコンサルタントとしての経験を活かせると思い、自信を持って入社しました。
新谷哲:その会社での思い出はございますか?
松岡真功:製品を作りましたが、顧客基盤を築けず倒産してしまいました。会社がなくなるという経験は初めてでしたね。今振り返ると、起業してよかったと思えるのはこの経験があったからです。今は会社を作ることはネットで簡単にできますが、会社を畳む経験はなかなかできない。これは本当に辛いものです。お客様がいるのに資金がなく、続けられない。お客様は「続けてほしい」と言ってくださるのに、それに応えられない。そのクローズの仕方が非常に難しいと感じました。この経験から、起業の際のアンチパターン、つまり「こういうケースではうまくいかない」ということを学びました。今でも「なぜうまくいかなかったのか?」と振り返るのはこの会社のことです。
新谷哲:社長にとっては、倒産を経験した企業にいたことが大きな学びになったということですね。
松岡真功:本当にそう思います。当時を思い返すと、売上が上がらない中で「技術者が欲しい」という求人を見て入社しました。そして最終的にはCTOとして製品を作り、社員や株主からは評価をいただけましたが、マーケティングや販売のリソース、そして資金が足りずに続けられなかった。会社が傾くと人が減っていき、フロアも縮小していく。その光景を体験しました。ただ、失敗には必ず原因があります。うまくいくことは運やタイミングもありますが、うまくいかないことには必ず理由がある。その原因を冷静に振り返る癖がついたのは、この時の経験からです。大きな学びだったと思います。
新谷哲:その後、起業前にアメリカのサン・マイクロシステムズ日本法人に移られたそうですが、理由は何かあったのですか?
松岡真功:サン・マイクロシステムズは、今のAndroid端末にも搭載されている「Java」という技術を生み出した会社です。今はもうありませんが。私は1996年か1997年ごろにプログラミングを始めた時、本屋で「Java」という新しい言語の本を手に取ります。「新しい言語を学ぼう」と思って挑戦したのですが、それが非常に印象深く「将来この会社に入りたい」と憧れていた会社でした。ベンチャーが倒産し、「次はどこへ行こう」と考えた時に、ふとその憧れを思い出し、サン・マイクロシステムズに入社することを決めました。
新谷哲:入社しようと思ったら、すっと入れたですね。やはり松岡真功社長は優秀ですね。
松岡真功:タイミングが良かったのかもしれません。面談というのは「出会い」だと思います。私を面接された方が非常に理解のある素晴らしい方で「この人と一緒に働きたい」と思えました。スキルや給与ももちろん大切ですが、面談で話が通じなければ、その後も通じない。他の会社も受けましたが、時間をかけて理解してもらうよりも30分の面談で「話が通じる」と感じられる会社に行こう、という考えでした。相性と運が良かったのだと思います。
新谷哲:その後、ご自身で株式会社BlueMemeを創業されますが、創業のきっかけはございますか?
松岡真功:創業のきっかけは、大きく2つあります。1つは、新卒で入社した会社で「いつか起業しろよ」と社長に言われ続けていたこと。もう1つは、倒産した会社の株主であるベンチャーキャピタルの方から「君は起業したらどうか」と言われたことです。倒産に対して責任を感じつつも、「これはチャンスを与えられているのかもしれない」と思いました。実はサン・マイクロシステムズに入る直前にその話を聞いていて、それ以降も定期的に「起業したらどうか」と言われ続けていました。「チャンスは人生でそう何度も訪れるものではない。この機会をつかんだほうがいいのではないか」と考えたのが大きなきっかけです。ですので、私の場合は「起業する」と決めたタイミングが先にあって、「どんな事業をやるか」を考えたのは後です。ベンチャーキャピタルから資金を受けるので「IPOを実現するために、どんな事業をやるか」を考えたことは、他の方と少し違う点かもしれません。
新谷哲:当初から「上場」を目標に事業を考えられたのですね。珍しいパターンです。
松岡真功:今では「上場を目指すためにこの事業をやる」という考え方も増えましたが、当時は「今やっている事業を成長させて上場する」というのが一般的でした。私は一度、会社がなくなる経験をしているので、次は絶対に成長させようという思いが強かったのです。最初は「どんな事業をやろうか」と非常に悩みました。手っ取り早く数字が伸びる分野に行くべきかとも思いましたが、最終的には原点に戻りました。SAP時代に触れた業務システム、自分が最も興味を持ちつつ理解しきれていなかった領域。そして金融など、企業向けのシステム開発。こここそが日本企業に価値を提供できると考え、この分野を選んで起業することにしました。
新谷哲:創業をする上で「怖さ」などはございましたか?
松岡真功:創業時の怖さは、確かにあります。ただ、私の経歴を振り返ると、在籍してきたのはベンチャー企業か外資系企業です。証券会社も、取引が少ないところからどんどん関係者が増えていくような成長過程を経験しましたし、いわゆる「普通の日本企業」には在籍しておらず、私の中で会社は「どんどん伸びるか、潰れていくか」というイメージで、常に変化し続けるのが当然だと思っていました。「安定しなければいけない」という発想があまりなく、創業そのものに対する怖さはなかったです。むしろ、安定するほうが逆に不安で、「もっと成長し続けないといけない」と思っていました。だから、本当の意味での怖さは、創業後しばらくしてから出てきたという感じです。
新谷哲:その「怖さ」とは、例えばどんなことで悩まれるのでしょうか?
松岡真功:いくつかありますが、ひとつは「従業員を増やしていったときに、本当に事業を継続できるのか」という点です。自分が選んで立ち上げたビジネスが、この先本当に広がるのかどうか。面白さと同時に怖さがあります。これは1人暮らしを始めたときの感覚に似ていると思います。1人暮らしをすると、朝起きたら部屋が昨日の夜のまま残ります。当たり前ですが、実家だときれいに片付いている。この違いは起業にもそっくりで、社長が動かなければ会社も昨日のままです。だからこそ意思決定をどんどん早くしていかないと、会社は変わらない。そのことが、怖さでもあり、面白さでもあると感じます。あとは「従業員をちゃんと守っていけるのか」という点ですね。会社を拡大していく過程で、「30人の壁」「3億円の壁」などとよく言われますが、自分の会社がその壁に近づいていると感じると、やはり怖さを覚えることがありました。
新谷哲:上場に向けてのご苦労はございましたか?
松岡真功:上場に向けては、本当にたくさんありました。上場を目指すと「支援しますよ」「コンサルしますよ」と、いろんな関係者が来ます。実際にコンサルを雇って上場資料やIR書類をたくさん作ってもらいますが、どうも腑に落ちない、納得できない部分が多く「本気度が足りないな」とか思いました。私の悪いところなのですが、外部にお願いして作ってもらったものが気に入らないと、自分で作り直してしまうんです。そうすると「せっかくやったのに、なぜやり直すの?」と周りに迷惑をかける。でも私は「あと3日あればもっと良いものができる」と思ってしまいます。相談して一緒に作るより、自分でやったほうが納得できるものが早くできると考えてしまう。結果、周囲をかなり振り回してしまいましたね。苦労というより、周りが苦労したと思います(笑)。
新谷哲:やはり気質として「何かを作り出したい」というエネルギーが強いのですね。
松岡真功:そうです。何かが目の前にあれば、それをベースにもっと良いものを作りたい。だから他の人が作ったものや外注した成果物も無駄にはなっていません。だってそれを見て「もっと良いものを作ろう」と思えたわけですから。ただ、周りからは「無駄にした」と見えます。その感覚がなかなか合いませんが、そこで気づいたのが「アジャイル」という言葉でした。前のものをもとに、どんどん新しいものを作っていく。これがアジャイルです。この理念を会社の文化にしようと思ったのが、今のBlueMemeです。採用活動もアジャイルの考え方に基づいています。10年後に今の事業があるかは分からない。でも常に継続性を考え、必要ならピボットしていけば良い。ずっと同じことをやる必要はない。そういう「ピボットしやすいビジネスモデル」を作ることに、上場までの間はかなり苦労しました。
新谷哲:株式会社BlueMemeの事業内容をお教えいただけますか?
松岡真功:当社は「業務システム」と呼ばれる分野を中心に事業を行っています。販売管理や生産管理、人事や経理といった業務システムですね。会社が小さいうちはパッケージをそのまま使うことも多いですが、企業が成長するとITが差別化の要因になってくる。そのため、大企業ではテーラーメイドのシステム開発が必要になります。日本企業は特にその傾向が強く、この領域はものすごい人員が関わり、人海戦術で作られてきました。私がSAPにいた頃は、数十億円規模のプロジェクトに300人ほどが関わって、ようやく1つのシステムを完成させます。IT業界は潤いますが、本当に顧客の競争力が高まっているのか疑問に感じています。そこで私は「10人でやる仕事を1人で、100人でやる仕事を12人〜13人で実現できる仕組み」を作ろうと考えました。結果、最低でも従来の3分の1の期間と人数でシステムを構築できました。この効率化こそが、当社のメイン事業になります。

新谷哲:ここからは全く違う質問をいたします。事前に好きなもの、好きな事をお聞きし「日本茶」と「わからないことを調べたり分析したりすること」とお答えいただきました。日本茶についてですが、どこの産地のお茶をよく飲まれているのでしょうか?
松岡真功:日本茶は、親戚が作っているお茶が大好きです。熊本の錦町というところに親戚のお茶畑がありまして、物心ついた頃からずっとそのお茶を飲んでいます。今でも毎日欠かさず飲んでいて、机の上にはペットボトルのお茶が常に5本〜6本並んでいますね。
新谷哲:日本茶の魅力はどんなところにあるとお考えでしょうか?
松岡真功:私は夏でも温かいお茶を飲みます。ペットボトルの温かいお茶は夏には売っていませんので、会社に保温できる容器を用意したり、急須で淹れたりします。お湯を沸かして茶葉からお茶を淹れるという行為、その時間が実は大切で、いろんなことを振り返ったり考えたりする時間になっています。さらにお茶のやさしい香りや自然を感じられるところが好きですね。落ち着けるし、すっきりと気持ちが切り替わります。
新谷哲:座右の銘もお聞きして「賢く失敗すること」とお答えいただきましたが、こちらを選ばれた理由はございますか?
松岡真功:「Fail Fast(フェイルファースト)」という言葉がとても好きです。人生でも会社でも失敗は避けられません。ただ、遅いタイミングでの失敗は大きなダメージになります。だからこそ、できるだけ早く失敗することが大事です。世の中には「分からないこと」が2つあると思っています。1つは未来、もう1つは他人の心の中です。対話していても「相手は何を求めているのだろう」と分からないことがあります。この2つの不確実性を減らすには、とにかく早めに試して失敗し、そこから残ったものを正解にしていくしかない。だから私は「失敗を恐れず、早く、賢く失敗する」ことが重要だと思っています。プライドを捨てて未完成の資料でも出して、見てもらう。これが起業においても非常に大切だと考えています。
新谷哲:次が最後のご質問です。全国の経営者、これから起業する方に向け、経営者として成功する秘訣をお教えください。
松岡真功:成功の秘訣は、今お話ししたことと重なる部分が多いですね。とにかく選択肢はたくさんあるので、まずは早く試してみること。そして「頑張って汗をかいてやる仕事」は楽しいのですが、それだけでは10年、20年と持たないです。私は若手社員や新卒にもよく伝えているのですが、たくさん試してみる中で「自分は苦労せずできるのに、他の人にはできない」ということに気づく瞬間があります。そこが自分の得意分野であり、強みです。その強みを見つけてフォーカスし、突き詰めていくことが大事だと思います。
新谷哲:松岡真功社長、本日はありがとうございました。
松岡真功:ありがとうございました。
編集後記
今回は、松岡真功社長でした。少しユニークでありながら、得意分野をしっかり持ち、謙虚で、豊富な経験を活かして企業を成長させている経営者だと感じました。頭の回転も早く、お話も分かりやすく、まさに「社長になるべくしてなった方」という印象です。最後にいただいた座右の銘「フェイルファースト ― 早めに失敗する、どんどん失敗すること」。これは私自身も大変勉強になるお話でした。ぜひ「早めに失敗する」ことを意識して、より良い企業づくりをしていただければと思います!
松岡真功氏
株式会社BlueMeme 取締役会長
1998年に大学卒業後、ソフトウェア開発会社でキャリアをスタート。以降ネット証券会社で独自システム開発、2001 年からは SAP で基幹業務システム導入におけるコンサルティングに従事。その後ベンチャー企業において技術開発を経験。BlueMeme創業前は米国サン・マイクロシステムズの日本法人で、ローコード技術による大規模システム開発及びクラウド技術の推進に携わる。
こうした経験を背景に2009年BlueMemeを創業。業務システムのコンサルティング事業開始後、学生時代から 25 年近く取り組んできたローコード技術(モデル駆動型開発技術)による業務システム開発の実現を積極的に推進。2013年には OutSystems と日本国内における総販売代理店契約を締結。先進的な取り組みを進める大手および中小企業に、業務システムが抱える技術者不足や高コスト体制、グローバル化への対応等のシステムインテグレーションが抱える構造的な課題の解決を行っている。2021年、東証マザーズ市場(現 東証グロース市場)に上場。
※本インタビューへの出演をご希望の方はこちらよりご応募ください。
本インタビューは、Podcast「社長に聞く!in WizBiz」で配信中の経営者インタビューを編集したものです。文中に登場する社名、肩書、数字情報などは、原則、収録当時のものですので、予めご了承ください。
今回は、松岡真功氏(株式会社BlueMeme 取締役会長)の経営者インタビューを取り上げました。
株式会社BlueMemeの詳細はこちらをご確認ください。
https://www.bluememe.jp/
『社長の孤独力』抜粋版(PDF29ページ)
無料プレゼント中!
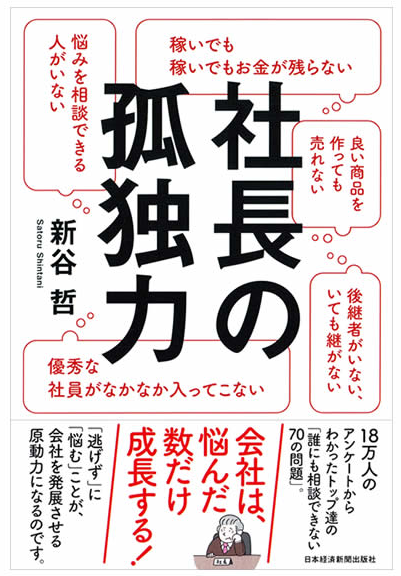 『社長の孤独力』(新谷哲/著) の【抜粋版】を無料プレゼントしております!
『社長の孤独力』(新谷哲/著) の【抜粋版】を無料プレゼントしております!
71の課題の中から「資金・人材・売上・採用・後継者」の5つを抜粋いたしました。銀行からお金が借りれない、社員がすぐに辞めてしまう、売上を伸ばしたい、など、具体的なお悩みの解決策が掴めます。ぜひご覧ください。
無料プレゼントの詳細はこちら