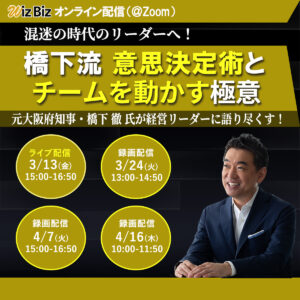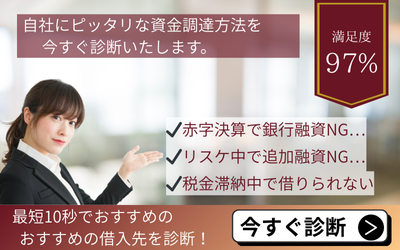本コーナーで掲載する経営者インタビューは、Podcast「社長に聞く!in WizBiz」で配信中の経営者インタビューを編集しています。今回、ご紹介する経営者は、山﨑徳之氏(ZETA株式会社 代表取締役社長)です。(2024年7月31日 2024年8月7日 配信)
本コーナーで掲載する経営者インタビューは、Podcast「社長に聞く!in WizBiz」で配信中の経営者インタビューを編集しています。今回、ご紹介する経営者は、山﨑徳之氏(ZETA株式会社 代表取締役社長)です。(2024年7月31日 2024年8月7日 配信)
今回は、ZETA株式会社(旧・サイジニア株式会社)の山﨑徳之氏にお越し頂きました。大学卒業後、ライブドアを始めとした様々な企業を経験したのち、旧ZETA株式会社を創業。そこから紆余曲折を経てZETA株式会社(旧・サイジニア株式会社)の社長に就任したエピソードから、経営のヒントが得られます。ぜひ、インタビューをお聞きください。
※2024年10月に「サイジニア株式会社」から「ZETA株式会社」に商号変更されました
新谷哲:本日の経営者インタビューは、ZETA株式会社(旧・サイジニア株式会社)の山﨑徳之社長です。まずは経歴をご紹介します。1995年デジタルテクノロジー株式会社入社。その後、株式会社アスキー、ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社を経て、株式会社オン・ザ・エッヂ(その後の株式会社ライブドア)に入社。こちらで取締役、代表取締役になられた後、旧ZETA株式会社を創業され、代表取締役にご就任。その後、ZETA株式会社(旧・サイジニア株式会社)の代表取締役社長となられました。山﨑徳之社長、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
山﨑徳之:よろしくお願いします。
新谷哲:最初の質問です。ご出身はどちらですか?
山﨑徳之:長野県の佐久市です。
新谷哲:小学校時代はどのようにお過ごしになりましたか?
山﨑徳之:小学生の頃は土地柄的にも時代的にも今と違って競争が激しくなく、少し成績が良い普通の子供という感じです。どちらかというと大人しい方だったと思います。
新谷哲:中学校時代はどのようにお過ごしになりましたか?
山﨑徳之: 4つの小学校から自動的に進学する形の中学校だったので、1学年の人数が増えただけというイメージです。
新谷哲:中学校時代の思い出はありますか?
山﨑徳之:普通に楽しく勉強をやっていました。英語の先生と馬が合って長野県の英語のスピーチ大会に出場しましたが、小学生の頃と同じで大人しい子供という感じでした。
新谷哲:高校も長野県の佐久市ですか?
山﨑徳之:はい、野沢北高校という進学校に進みました。私の住んでいた地域では、東京の大学に進学するには、野沢北高校へ進学する以外に方法がありませんでした。こちらへは普通に一般受験をして進学しました。
新谷哲:では、成績がよろしかったのですね。
山﨑徳之:私自身、不思議だと思うのですが、成績はいつも「上から少し下くらい」の位置でした。例えば、中学では学年1位にはなれず10位くらい。高校は受験を経て優秀な人が集まるので、普通なら相対的に順位が下がるはずですが、高校も学年で10位くらいの位置でした。
新谷哲:高校時代はどのようにお過ごしになりましたか?
山﨑徳之:進学校だったので、小学校・中学校時代に比べると勉強に関する話題が多く、友達関係は若干積極的でした。みんなが趣味を持ち始める頃だったので、趣味ごとにそれぞれ繋がっている友達関係、今で言うソーシャルネットワークのようなものがあった感じです。
新谷哲:大学はどちらに進学されましたか?
山﨑徳之:青山学院大学です。学習院大学にも合格したのですが、担当の先生から「青山学院大学の方がいいのではないか」と言われ、深く検討せずに青山学院大学を選びました。
新谷哲:大学時代の思い出を教えてください。
山﨑徳之:理系の電気電子工学科に進学し、勉強ばかりしていました。専門の授業に関しては一度も欠席せず、受けた単位は全て合格しました。評価も高く、4年生の時は専門分野だけであれば1位の成績でした。専門分野に関しては、それがやりたくてこの大学に進学したので、全ての授業を最前列で受けて、テストでも良い成績を収めていました。
新谷哲:では、優等生だったのですね。
山﨑徳之:好きなことだったのでやりたいことをやっていた、という感じです。
新谷哲:卒業後はデジタルテクノロジー株式会社に入社されますが、新卒での入社でしょうか?
山﨑徳之:はい、新卒です。私が入った研究室では、「話者認識」という話している声からそれが誰なのかを分析する技術を研究していました。現在のAI技術の先駆けのようなことですね。事前にそれを調べていたわけでなく、「この教授の授業が面白い」と思いその研究室に入りました。研究には非常に高い計算能力が必要で、電気電子工学科の中でも特にコンピューター設備が充実していました。研究をしていた1994年は、日本ではまだインターネットは一般的ではありませんでしたが、大学ではすでに導入されており、Eメールなどが利用できる環境が整った、数少ない場所でした。この影響で、研究よりもインターネットに興味を持つようになりました。就職活動をする中でいくつかの会社を廻り、「御社ではインターネットにどう取り組む予定ですか?」と質問をしました。ほとんどの会社は「インターネットは遊びのもの」「将来どうなるかは分からない」という答えでしたが、唯一、インターネットに力を入れていた会社があり、それがデジタルテクノロジー株式会社でした。第一志望だったため面接を受け、最初に内定をいただき、短期間で就職活動は終了しました。大学の研究も早めに終わっていたので、10月頃から前倒しでアルバイトとして働き、仕事を覚えていきました。今で言う「インターン」のような形ですね。
新谷哲:山﨑徳之社長は先見の明がおありなのですね。
山﨑徳之:先見の明とまでは言えないですが「こんなに面白くて可能性の高いものなのに、遊びだからやらない、と言うのはなぜだろう?」とは思っていました。たまたま入った研究室の環境が整っていたので、幸運な面もあると思います。
新谷哲:デジタルテクノロジー社での思い出はございますか?
山﨑徳之:私はエンジニアとして採用されました。同期は、私を含めたエンジニア4名と営業3名から構成される総合職が7名と、事務職が2名でした。当時、入社時点で私が一番UNIXなどに詳しかったと思います。ところが、入社前の懇親会で、右に社長、左に会長が座る席で、2時間ほど「君は営業の方が向いていると思うよ」と説得されました。私は「技術がやりたいのでエンジニアでいきます」と断り続けていましたが、最後に社長から「でも、そう言われているうちが花だよ」と言われて「分かりました。じゃあ営業をやります」と返事をしてしまい、営業職に配属されることになりました。その社長に先見の明があったのか、1年目からトップセールスのような成績を出すことができました。インターネットという新しい分野だったので、技術に詳しい営業が求められ、自然とお客様に選ばれたのです。その点では会社の判断は的確だったと思います。ただ、私自身は技術をやりたくて入社したので、少し複雑な気持ちでした。営業に配属されている間に、同期のエンジニアたちがどんどん技術力を伸ばしていくのが顕著になっていき、入社前のアルバイト期間を含めて約2年で転職することを決めました。
新谷哲:転職先として、株式会社アスキーを選ばれた理由はございますか?

山﨑徳之:アスキーは私のお客様のうちの1社でしたが、そこには非常に優秀な技術者の方がいて、その人に憧れて「こんなエンジニアになりたい」と思い、アスキーの面接を受けて採用してもらいました。しかし、入社から3ヶ月ほどでその人が独立すると言って退職され、目当ての人がいなくなってしまいました。さらに、私が配属されたのは、当時アスキーが運営していた3つのプロバイダーのうち、「アスキーインターネットフリーウェイ」という新しく始まった無料プロバイダーの部署でした。ちなみに、他の2つは「アスキーAIX」という花形のプロバイダーと、「アスキーネット」というパソコン通信サービスでした。私が憧れていたエンジニアの方は「アスキーネット」のメインエンジニアでありながら、「アスキーインターネットフリーウェイ」のサポートもしていました。その方が退職され、「アスキーインターネットフリーウェイ」はハイパーネットという外部の会社と提携して運営されましたが、私が入社して1年ほどでハイパーネットが倒産してしまい、事業自体が続けられなくなりました。結果として、アスキーにはわずか11ヶ月しか在籍できませんでした。
新谷哲:アスキーでの思い出はございますか?
山﨑徳之:エンジニアは私ぐらいしかおらず、大変な状況でした。それまでパソコン通信側でプロジェクトを取り仕切っていた優秀なエンジニアの方も退職してしまい、自分で全て対応するしかありませんでした。私はまだ駆け出しのエンジニアで、経験も浅い状態でした。さらに、使用していた機器はトラブルが頻発するもので、週に2〜3回は夜中に「トラブルが発生しました」と連絡が入り、現場に駆けつけて対応するという日々を過ごしていました。形式上、上司はいたので「まだ新人のエンジニアですので、たまには対応していただけませんか」と上司にお願いしたところ「私は分からないから君に任せる」と言われてしまい、結局は自分で解決するしかありませんでした。そんな環境の中で、必死に走り続けていたというのが当時の状況です。
新谷哲:その後、ソネット(ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社)に転職されていますが、経緯を教えていただけますか?
山﨑徳之:ハイパーネットが倒産し、事業自体が継続できなくなったため、転職せざるを得ない状況となり、IIJ(株式会社インターネットイニシアティブ)とソネットの2社に転職活動を行いました。IIJでは最終面接まで進みましたが、当時の会長とのやり取りがうまくいかず不採用となりました。一方、ソネットは、当時はまだソニーからの出向社員が中心で、プロパー社員を採用する初めてのタイミングでした。私はその「プロパー1期生」として、幸運にも採用されることになりました。同じタイミングで採用された同期は7~8名ほどいました。後日、採用担当の女性リーダーの方から「君は絶対に落ちると思っていた」と言われたのですが、幸いにも採用していただけたことに感謝しています。こうして、エンジニアとして2社目のキャリアをスタートすることができました。
新谷哲:ソネットでの思い出はございますか?
山﨑徳之:ソネットで私が配属されたのは、サーバーチームでした。サーバーやUNIXに関わる業務が中心という、まさにやりたかった分野だったので歓迎すべき配属でした。そのチームには非常に優秀なエンジニアの方がいました。東工大出身で、UNIXに関する知識がとても豊富な方でした。しかし、私が入社して間もなく「もう業務が回ると思うから」と言い残して、ほとんど出社しなくなったのです。今振り返ると、当時はそれでも許される時代だったのだと思います。ただ、その方は出社されないだけで、相談すれば丁寧に対応してくださいました。アスキー時代と比べると、1年間の経験を積んでいた分、少し余裕を持って取り組むことができました。ただ、ソネットは当時急成長していた会社だったため、忙しさで言えばアスキー時代を上回っていたように思います。そのような環境の中で、自分自身のエンジニアとしての成長を感じつつ、充実感を持ちながら楽しく頑張っていました。
新谷哲:その後、株式会社オン・ザ・エッヂにご入社されますが、どのような経緯でしょうか?
山﨑徳之:私がソネットに入社した当時、会員数は約100万人ほどでした。退職する頃には約400万~500万人まで増加していたと思います。入社時点では、比較的小規模なシステムが構築されていましたが、急速な会員数の増加により、既存のシステムでは対応しきれない状況になりました。そのため、システムを一から見直し、片っ端から作り直していくことになりました。2年ほどかけてすべてのシステムを再構築し、ようやく安定した環境を整えることができました。ひと段落したところで私は「法人向けのデータセンタービジネスに挑戦したい」と考えるようになり、会社に相談をしました。しかし、当時のジェネラルマネージャーからは「今は個人向けしかやる予定はない」と回答を受けました。この方針自体に不満はありませんでしたが、自分の興味が法人向けビジネスに向いていることを感じました。その頃、リングサーバーネットワークという、プロバイダー業界の主要なエンジニアたちが集う飲み会に参加していました。その場で「データセンターに興味がある」と話したところ、オン・ザ・エッヂの当時のCTOの方が「当社はデータセンター事業を始めたばかりで、ぜひ参加してほしい」と声をかけてくださいました。そこで、ソネットのジェネラルマネージャーに相談したところ反対はされず、「それも良い選択だと思う」と背中を押していただきました。こうした経緯から、私はオン・ザ・エッヂへの転職を決断しました。
新谷哲:オン・ザ・エッヂ(後の株式会社ライブドア)での思い出はございますか?
山﨑徳之:こちらも大変な経験をしました。あまり人のことを悪く言うのは控えたいところですが、「ぜひ来てほしい」と私を誘ってくださった前任のCTOの方はプログラミングには非常に優れている一方で、サーバーやネットワークについては商用向けの知識や経験が十分とは言えませんでした。そのため、ネットワークの設計は家庭用のネットワークを拡大したような形で始められており、商用サービスとしては不十分な状態でした。しかし、サービス自体は既に稼働しており、一部ではお客様も利用している状況でした。そのため、私は「このままではとても持たない」と感じ、サービスを止めずにシステムを作り直す必要があると判断しました。ネットワークも現状では不安定で、もしも障害が発生したら大きな問題になりかねませんし、IPアドレスの設計も将来的なお客様の増加に対応できるものではありませんでした。そのような課題を抱えた状態だったため、片っ端から見直しを進める必要がありました。特に最初の3ヶ月間は非常に忙しく、ほとんど家に帰ることができませんでした。徹夜が続き、稼働中のシステムを止めないよう慎重に対応しながら、必要な部分を次々と改良していく日々が続きました。その後約1年半が経過した時点で、取締役に選任されることになりました。このタイミングで、堀江さんと宮内さんを除く全ての取締役が入れ替わるという大きな人事異動がありました。新しい取締役メンバーは各部門から選ばれる形となり、私はエンジニア出身の取締役として選任されました。
新谷哲:堀江さんとのやり取りで思い出などございますか?
山﨑徳之:年齢は私が1歳年上で同世代でした。堀江さんはすごく頭が良い方でした。意見が一致することが8割程度と多かったのですが、時には意見が対立し、議論が白熱することもありました。堀江さんは記憶力が非常に優れていて、それが議論の中で強みとして発揮されていました。私自身、論理的な部分では優位に立っていると感じる場面もありましたが、堀江さんは膨大な記憶から次々とエビデンスを引き出し、それによって私が負けてしまう、ということがよくありました。その度に「この方は本当に優秀だな」と感心していました。
新谷哲:いわゆるライブドア事件の頃は、どのような状況だったのですか?
山﨑徳之:私もライブドアでデータセンターの再構築を進め、2年ほど経ってようやくひと段落つきました。この時点で「もう任せても大丈夫だ」と思える体制が整ったため、次に何をするべきか考え始めたところ、堀江さんが「日本の電話システムは利権の塊であまり良い状況ではない」と話しており、それをきっかけに私はIP電話に関する調査を始めました。調査を進めるうちに、IP電話やVoIP(ボイスオーバーIP)技術に非常に興味を持つようになり、どんどんのめり込んでいきました。ただ、当時の日本では大手企業が市場を寡占しており、技術や情報がほとんど表に出てこない状況でした。例えば、NTTや沖電気、NECなどが優れた技術を保有していましたが、それらは外部からアクセスできるものではなかったのです。そのため、もっと開かれた情報を探そうとすると、シリコンバレーに行くしかないという結論に至りました。そして私は「シリコンバレーで起業しよう」と決意し、その旨を会社に伝えたところ、「エンジニア担当の役員がいなくなるのは困る。非常勤でも良いから残ってほしい」と頼まれました。私もその要望を受け入れ、非常勤で取締役を続けながらシリコンバレーに渡り、VoIP関連の会社を立ち上げることになりました。非常勤の間、取締役会にはリモートで参加していました。その後、日本にいた時は地味でテクノロジー志向の会社だったライブドアが、私がアメリカに渡るタイミングで六本木ヒルズにオフィスを移転し、急速に世間の注目を浴びるようになりました。ちょうどその頃、「野球球団を買収する」「ニッポン放送を買収する」といった話題が次々と出て、私が日本を離れている間に、ライブドアは一躍有名な企業となっていました。アメリカでは、日本人向けの新聞「BaySpo」に毎週のようにライブドアの記事が掲載されており、現地の友人からも「これお前の会社だろう?」と言われることが多くなりました。ただ、私自身は現場の実感があまりなく、不思議な気持ちでその状況を見ていました。私の取締役としての役割は、システム改善の提案や、コストに関する助言を行うといったもので、派手な話題の渦中にいるという感覚はほとんどありませんでした。それでも、遠くからライブドアの急成長を目の当たりにして、不思議な感覚でその変化を眺めていました。
新谷哲:その後、代表取締役になられますが、これは「ならざるを得ない」という感覚で就任されたのでしょうか?
山﨑徳之:ライブドア事件が起きた当時、私はアメリカにいました。時差の関係で寝ていたのですが、会社からの連絡ではなく、日本にいる友人から会社が大変なことになっていると電話がかかってきてその事態を知りました。その時点ではテレビを見ることもできなかったので、ネットニュースを確認すると、事件がニュースのトップに大きく取り上げられていました。しかし、会社からは特に何の連絡も情報も来ない状況で、私は一般の人と同じ情報量の中で事態を見守るしかありませんでした。その後、事件の規模がどんどん大きくなり、「これは一度日本に帰国しなければならない」と判断し、帰国しました。会社では「もし堀江さんが逮捕された場合には熊谷さんが代表取締役に就任し、熊谷さんも逮捕された場合には私が次の代表取締役になる」という決議がなされていました。そして実際に、堀江さんと熊谷さんが逮捕される事態となり、その取り決め通り、私が代表取締役に就任することになりました。
新谷哲:アメリカの会社はどうなったのですか?
山﨑徳之:日本とアメリカを1週間おきに行き来していましたが、「こうなった以上しょうがない」と会社をたたむ決断をしました。アメリカで会社をたたむ作業をしつつ、また日本に戻ってくるという生活をしていました。
新谷哲:すごく大変だったのですね。
山﨑徳之:人生大変なことばかりですね。
新谷哲:その後、ライブドアを退職することになりますが、どのような経緯があったのでしょうか?
山﨑徳之:退職するというよりは、私は「旧経営陣の一員」という位置づけになっていたので、代表取締役に就任した時点で退任することは決まっていました。新しい取締役を選任するには臨時株主総会を開く必要があり、その間も会社には代表が必要です。そのため、最初から「3ヶ月後に退任する予定での就任」という形で代表取締役に就任したという流れでした。
新谷哲:では後処理をするため、代表に就任されたのですね。
山﨑徳之:そういう感じです。
新谷哲:その後、旧ZETA株式会社を創業されますが、もともとはゼロスタートという名前だったのですよね?
山﨑徳之:ゼロスタートコミュニケーションズという名前で作って、その後ゼロスタートに変え、ZETAに変えたという形です。
新谷哲:こちらをご創業されたとき、どんな会社を作ろうと思われたのですか。
山﨑徳之:やりたくて起業したわけではありませんでした。ライブドアには残れず、かといって転職活動をするわけにもいかないので「自分で会社を作るしかない」と思い創業しました。そのため、強いモチベーションや具体的な目標はありませんでした。世間では起業することがもてはやされますが、私はそれほど良いものとは思いません。起業することは簡単ではなく、大変なことが多いです。特に私は明確なビジネスプランがあったわけでも「これで世の中を変えたい」という信念もなかったので、試行錯誤の連続でした。私はエンジニア出身なので、お金儲けやマネタイズの知識や経験が不足しており、起業から1年ほどで資金が底をつき倒産寸前まで追い込まれました。そこからなんとか這いつくばって立て直し、時間をかけて少しずつ会社を軌道に乗せ、状況が好転したという感じです。
新谷哲:その後、しばらく経ってからZETA株式会社の代表取締役に就任されますが、どのような経緯でしょうか?
山﨑徳之:ZETA株式会社の代表取締役就任は最近で、3年ほど前の出来事です。それ以前は会社が倒産しそうな状況に陥り、やむを得ず受託開発をしていました。しかし、受託開発だけでは未来がないと考え、自社製品の開発に取り組みました。最初は「利益が出なくてもいい」と始めた自社製品も、収益化までは約7年かかりました。自社製品が会社の成長を支える柱になり得る状況になり、受託開発などの他の事業はすべてやめました。自社製品に専念する体制に切り替えてから、4年ほどで会社も軌道に乗りました。ちなみに、ZETAもサイジニアもレコメンド事業から始まっています。ただ、レコメンド事業自体はあまり収益性の高い分野ではありません。当時はこの分野が盛り上がり、レコメンド事業で起業した会社が多かったですが、現在ではレコメンド事業をメインにしている企業はほとんど残っていません。サイジニアとのやり取りは2019年頃のことで、共通の知人を通して「どちらかがどちらかのレコメンド事業を買いませんか?」という話が持ち上がりました。いわゆる合従連衡のような話だったのですが、金額面で折り合いがつかず、結局はまとまりませんでした。その後、再び会う機会があり、その時にひらめいて「いっそのこと会社を一緒にするのはどうか?」と提案したところ、サイジニアの方から「それはすごくいいですね」という返事がありました。その時点でサイジニアは業績があまり好調ではなく、株価も堅調とは言えない状況でした。一方、ZETAは軌道に乗り始めていたため、最初はなかなか話がまとまらず、2年間ほどつかず離れずの関係が続きました。その間、何度も破談になりかけましたが、サイジニアから「他のM&Aの案件もあるので、そろそろ決めていただかないと」という声がありました。それに対して「それならやめても構わない」という気持ちもありましたが、最終的には話が決裂せずに続きました。そして、約3年前、いよいよ期が熟したと感じて本格的に交渉を始めました。そこからは順調でデューデリジェンスも無事に進み話がまとまりました。
新谷哲:大変面白く、素晴らしい勉強になるお話でした。ありがとうございます。次はZETA株式会社の事業内容をお教えいただけますか?
山﨑徳之:2021年にM&Aを行い、旧サイジニアは旧ZETAを完全子会社化しました。当時、売上はサイジニアが上でしたが、利益はZETAの方が多かったという状況です。サイジニアは当時、広告事業をメインとしており、さらにMEO事業も行っていました。一方、ZETAはCX改善事業を中心に展開していました。M&A時には、この2つの事業を柱として会社を成長させていこうという計画でしたが、M&Aから1年後、広告事業が急速に不調に陥りました。大手クライアントからの解約が続き、さらにCookie規制の影響もありました。そのため、1年ほど前に広告事業を思い切って売却しました。2本柱での成長戦略は1年で崩れた形となり、CX事業一本に集中する方針に切り替えました。2023年は非常に大変な1年で、筆頭株主のソフトバンクさんによる株の売却や、メイン事業の最大手クライアントからの解約がありましたが、なんとか期初の業績予想を超えて達成することができました。当初考えていたビジネスモデルは大きく変わりましたが、元々ZETAが手掛けていたCX事業が2022〜2024年で3倍ほど成長したため、自然な形でこの方向に進んだと思います。M&A決定前の年、ZETAの営業利益は約2億1,700万~2億1,800万円でしたが、2024年5月期は業績予想が6億2,000万程度となっており、今日、業績予想の上方修正を発表しました。この予想を超える勢いで業績が伸びており、非常に嬉しい成果だと感じています。
(その後2024年10月に吸収合併と商号変更を行い、「ZETA株式会社」として企業運営をしております)

新谷哲:ありがとうございます。ここからは全く違う質問をいたします。事前に好きなもの、好きなことをお聞きして「仕事、読書、猫、ゴルフ、お酒」とご回答いただきました。猫好きということですが、飼っていらっしゃるのですか?
山﨑徳之:飼っています。学生時代に一度猫を飼ったことがあったのですが、大学生1人で飼い続けるのは難しいと感じ、飼い始めて2〜3ヶ月で長野の実家に猫を預けることにしました。実家では犬や鳥も飼っていたので、猫の面倒を見てもらうことができました。その猫はかなり長生きしました。その後、10年ほど前から再び猫を飼い始めまして、現在は3匹目と4匹目の猫を飼っています。
新谷哲:癒しになりますよね。
山﨑徳之:猫は機嫌が良い時もあれば悪い時もあるので面白いですよね。犬の方が常に人間には良くしてくれる印象がありますが、猫は機嫌の上がり下がりがあるので面白いです。
新谷哲:次に座右の銘もお聞きして「Nothing is Impossible」とご回答いただきました。こちらを選ばれた理由を教えてください。
山﨑徳之:ソードフィッシュという映画から拝借しました。ヒュー・ジャックマンとジョン・トラボルタが主演のコンピューターの映画で、劇中で「Nothing is Impossible」というセリフがあり「私が思っていることと近い」と思いましたね。「諦めなければ何とかなる」という考えを言葉でうまく表現できていなかったのですが、それを言語化したときに「Nothing is Impossible」がピンときました。ただ、日本人の感覚では「Nothing is Impossible」というフレーズが少ししっくりこないかもしれません。というのも、否定形が2回続くため、どうしても「Everything is Possible」とはニュアンスが違って感じるからです。ナイキかアディダスが「Impossible is Nothing」という形でマーケティングをしていたことが思い出されますが、個人的には「Nothing is Impossible」の方がしっくりきました。
新谷哲:次が最後の質問です。全国の経営者、これから起業する方に向け、経営者として成功する秘訣をお教えください。
山﨑徳之:成功するには「信念を持って行動すること」が大切だと思います。先ほども少し言いましたが、私は起業が必ずしも良いものだとは思いません。もちろん、良い面もありますよ。例えば、画期的なビジネスモデルを思いついて、「これがあれば世の中を変えられる」と信念を持って起業する場合です。Googleがそうです。以前AltaVista(アルタビスタ)という検索エンジンが主流で、その後、リンクの重要性に気づいてページランクという概念が生まれ、それが世の中を変える可能性があり、実際に変わりました。そういった信念や確信を持って起業するのであれば素晴らしいと思います。しかし、私はファッション起業のようなケースが増えていることも事実だと思っています。「起業ってかっこいい」「誰かの会社で働くなんてつまらない」という理由で起業する人が多いのではないでしょうか。こうした考え方には疑問を感じます。起業自体を目的にするのではなく、やりたいことがあってこそ意味があるものです。例えば、日本でラジオを広めたい、バイクを広めたいなどの理由から創業した、ソニーやホンダのような企業がそれにあたります。起業は、自分が実現したいことがあってこそ成り立つものだと思います。また、大企業はとても優れている側面があって、特に未経験で社会のことがよく分かっていない若い人たちに効率よく物を教える仕組みが整っています。最初はしっかりと地道に勉強をして、その後に自分の進む道を考えるのが良いと思います。また、起業した後は会社を早く閉じることも選択肢の一つです。ダメなものにしがみついてズルズル続けるのも良くありません。しかし、外部の投資家や従業員がいる場合、簡単に諦めるのは良くないとも言えます。自分1人の都合で会社を閉じると、他の人に迷惑をかけることがあります。どうすべきかどうかは状況によりますが、信念を持って行動することが大切だと思います。最近『ユニクロ』の本を読んで、多くの感銘を受けました。やはり「世の中にとって良いことで、消費者のためになる」という信念がなければ成功しません。私たちの会社の場合は「デジタルマーケティングやECを通じて、消費者を幸せにする企業のお手伝いをすること」が信念です。消費者が幸せになること自体は間違っていないはずです。だから、頑張っていればいつか報われると思っています。つまり、挫けず諦めないことが大事です。ただし、挫けず諦めないことは重要ですが、その信念を持って会社が倒産してしまうのでは意味がありません。その場合は、信念が少し後回しになってでも、会社を生き延びさせることを最優先に考えることもやむを得ないと思います。しかし、実際には最初は「今は本意ではないビジネスをやって、いずれやりたいことを達成しよう」と思って始めた人が、意外にもそのまま別の方向に進んでしまうことが多いのも事実です。そうした方向に進むと、居心地が良くなってしまうこともあります。ですから、いずれ元々やりたかったことに戻ることを意識しておいた方が良いと思います。そうしないと、最終的には目標を見失った、ただ生きているだけの会社になってしまう可能性があるからです。結局、信念を持って、正しいと思うことを貫きながら、挫けずに頑張りつつ、会社を倒産させないように生き延びることが最も大切だと思います。
新谷哲:大変深いお話です。ありがとうございます。
山﨑徳之:やはり苦労はした方がいいですよ。今は残念ながら法的に長時間働くことは難しいですが、勉強をすることは良いことだと思います。「若い時の苦労は買ってでもしろ」という言葉がありますが、本当にその通りだと思います。私も30年かけて、今の会社が良い形になってきたのは、若い頃に多くの苦労をしたからです。当時は望んで苦労をしたわけではありませんが、その経験が今の自分にとって大きな糧となっています。やはり修羅場や鉄火場を経験することで得られるものは非常に大きいです。今、「働いたら負け」「辛いぐらいだったらすぐに転職した方が善だよ」などの意見が多いですが、私は必ずしもそうは思いません。法に反しているブラック企業でない場合に限りですけどね。大変な時期を乗り越えた経験こそが、将来的に花開く力になると思います。
新谷哲:山﨑徳之社長、本日はどうもありがとうございました。
山﨑徳之:ありがとうございました。
編集後記
今回は山﨑徳之社長でした。経歴もすごいですが、ご苦労もすごいです。苦労をした方がいい、とはっきりとおっしゃるところは、かっこいいです。挫けず、信念や社会のためということもおっしゃっており、座右の銘の「Nothing is Impossible」も本当に良いお言葉です。皆様もぜひ、山﨑徳之社長みたいに苦労をして、成功者になっていただければと思います。
山﨑徳之氏
ZETA株式会社 代表取締役社長
1996年11月 株式会社アスキー入社
1997年10月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社入社
2000年05月 株式会社オン・ザ・エッヂ入社
2001年12月 同社 取締役
2006年02月 同社(株式会社ライブドア)代表取締役
2006年06月 旧ZETA株式会社創業 代表取締役(現任)
2021年07月 ZETA株式会社(旧・サイジニア株式会社)取締役社長
2024年04月 ZETA株式会社(旧・サイジニア株式会社) 代表取締役社長(現任)
※本インタビューへの出演をご希望の方はこちらよりご応募ください。
本インタビューは、Podcast「社長に聞く!in WizBiz」で配信中の経営者インタビューを編集したものです。文中に登場する社名、肩書、数字情報などは、原則、収録当時のものですので、予めご了承ください。
今回は、山﨑徳之氏(ZETA株式会) 代表取締役社長)の経営者インタビューを取り上げました。
『社長の孤独力』抜粋版(PDF29ページ)
無料プレゼント中!
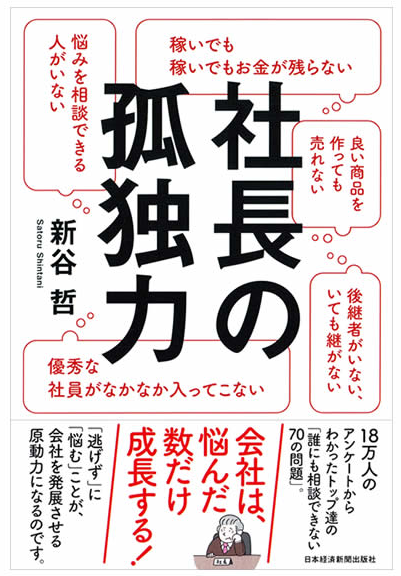 『社長の孤独力』(新谷哲/著) の【抜粋版】を無料プレゼントしております!
『社長の孤独力』(新谷哲/著) の【抜粋版】を無料プレゼントしております!
71の課題の中から「資金・人材・売上・採用・後継者」の5つを抜粋いたしました。銀行からお金が借りれない、社員がすぐに辞めてしまう、売上を伸ばしたい、など、具体的なお悩みの解決策が掴めます。ぜひご覧ください。
無料プレゼントの詳細はこちら